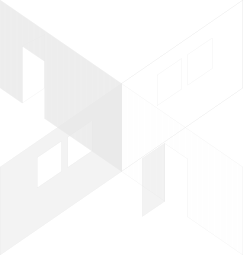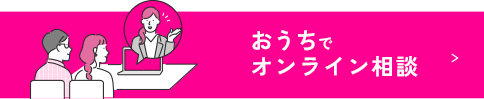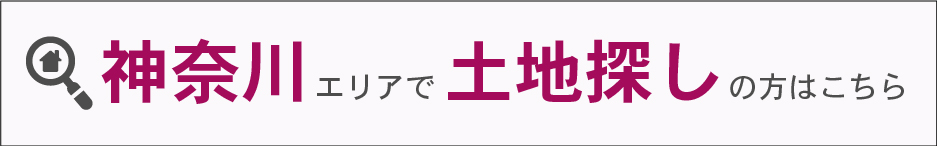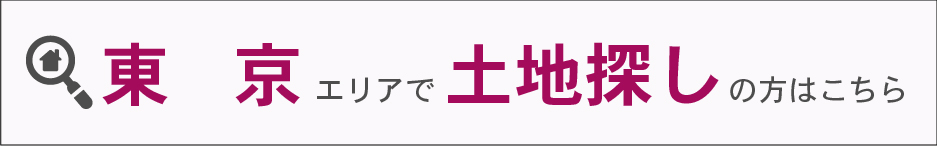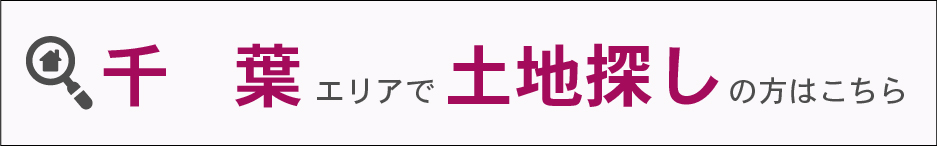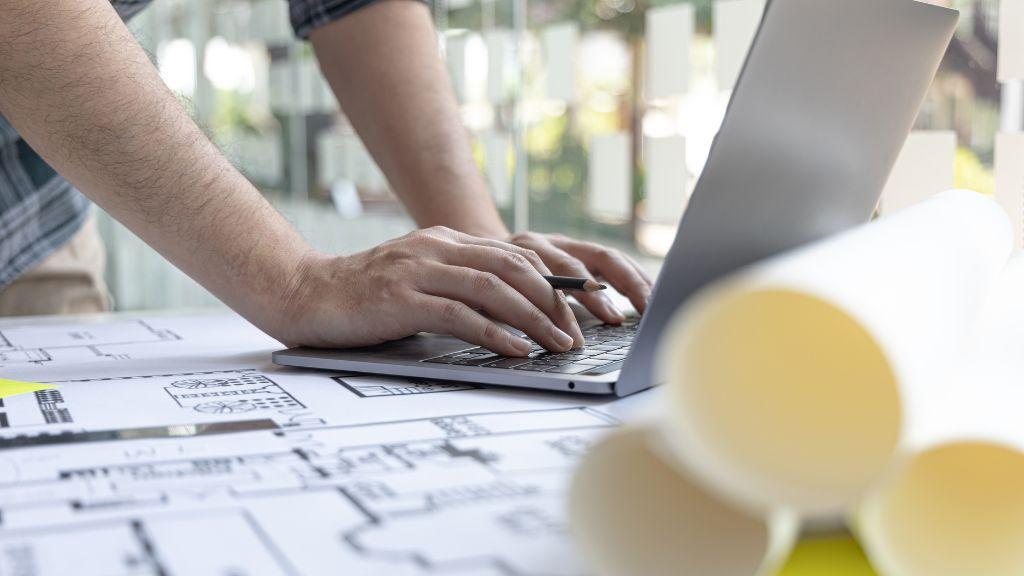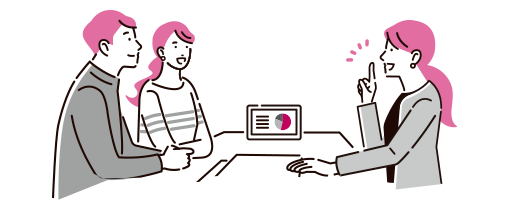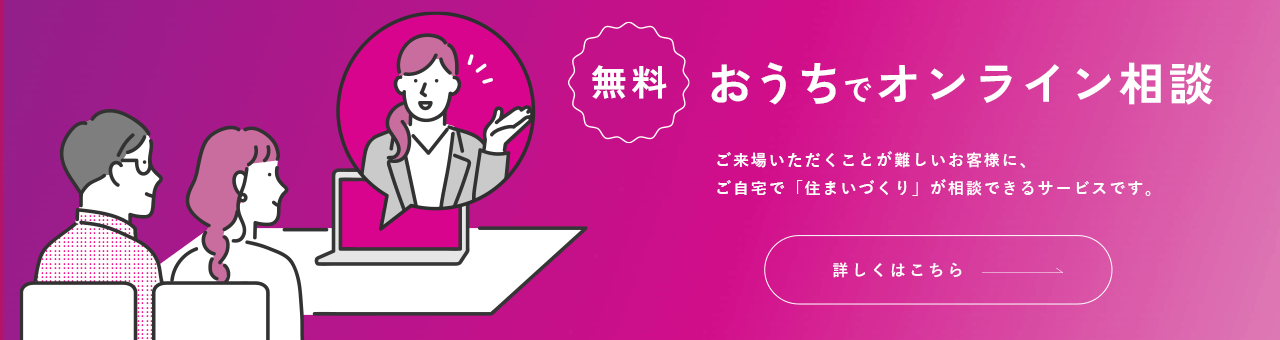目次
「予算の関係上、狭小住宅になりそう…。後悔するかな?」
一般的に、15坪以下の土地に家が建てられる場合に狭小住宅といわれます。
狭小といわれる住宅、購入後に後悔するのでは?と不安になる場面もあるでしょう。
本記事では、狭小住宅を建てた人が後悔しやすいポイントを解説、さらにその対策を紹介します。
・狭小住宅で後悔するポイントがわかる
・狭小住宅の後悔ポイントへの対策がわかる
・狭小住宅のメリットがわかる

狭小住宅を建てた人の後悔ポイント

狭小住宅を建てた人は一体どんな点に後悔しているのでしょうか。
後悔しやすいポイントを把握しておけば対策を立てることができるので、ひとつずつ確認してみましょう。
①3階建ての場合上下動がキツイ
狭小住宅は床面積を増やすため3階建てにする場合がありますが「上下動の辛さを感じる」ことがあるようです。
特に掃除や洗濯など、重量のあるものを持って移動する場合に実感します。
子供が小さいときも、キッチンやお風呂とリビングを頻繁に行き来するので負担に感じることがあるでしょう。
②隣の家との距離が近い
「隣家との距離の近さ」にため息をつくこともあります。
狭小住宅を選択する場合の多くは、土地面積いっぱいに家を建てます。
お隣も同じ考え方で建築し、結果として家と家の距離が手を伸ばせば届くほどの距離しかなくなります。
建物同士が近接すると、風が通らない・隣家の音が響くなど、デメリットを体感することとなるでしょう。
③日当たりが悪くジメジメしている
隣家との距離が近いことと関係しますが、「日当たりが悪く湿気を感じる」こともあります。
自宅と隣家の間にスペースがなければ風が通らず、基礎や外壁に湿気が溜まってしまいコケが生える場合も。
室内にも日光が届かず、風も吹かないので湿気が溜まり、カビが生えることが悩みのタネになります。
④メンテナンス性能が低い
敷地の周囲に余裕がないと、「メンテナンスが受けられません」。
2階、または3階建ての住宅の外壁や屋根の状態確認、メンテナンスを行うとき、必ず作業員のために足場が必要になります。
物件によっては足場を配置するスペースすらない場合があり、事実上メンテナンスを行うことができません。
万が一、壁面から降雨が浸透して漏水が発生しても、修理を行うこともできず室内側の応急処置しかできません。
⑤収納が少ない
「収納の少なさ」も、日々の生活の質を下げる要因になります。
狭小住宅の場合、床面積は限られておりLDKや水回り、寝室、子供室といった絶対に必要な部屋を確保していった結果、収納を削ることになるのです。
収納が少なければ、物がリビングやダイニングなど、団らんの場所まで広がってしまい清潔に暮らすことができません。
狭小住宅の後悔ポイント対策

狭小住宅に住んだときに後悔しやすいポイントをまとめましたが、対策はないのでしょうか。
ここから、後悔することが多いポイントを解消する工夫について紹介します。
①上下動の後悔を解消
階段の移動が辛い上下動は、「家事を効率化することで対処」できます。
洗濯であれば洗濯乾燥機を導入して洗濯から乾燥まで一緒に完了させ、濡れた洗濯物を持って階段を移動する手間を減らします。
掃除についても各階に小型の掃除機を設置すれば、掃除機を持ったまま移動する機会を減らせます。
設計段階で家事を行う姿をイメージして、可能な限り家事動作を削減することが大事です。
②隣家との距離感の後悔を解消
隣家との距離感は土地面積が決まっているため解消が困難ですが、「間取りの工夫で緩和を図る」ことができます。
通風の問題は隣家側、横方向から風を取り入れるのは困難なので、上下方向の通風で解決します。
具体的には2階から3階までを吹き抜けにして、3階に天窓か高窓を配置することで上に向かう空気の流れを発生させる方法です。
高い位置に換気扇を設ければ、さらに効率的に風を取り入れられるでしょう。
隣家からの音の響きも対処が困難ですが、隣家側にクローゼットや押入れ、トイレを配置することで緩衝帯を設けて対処することができます。
③日当たりの問題を解消
日当たりの問題も隣家との距離感で紹介した「吹き抜け・高窓の導入」で解消を図ることができます。
さらに、道路側に大きな開口部を設けることで日光を招き入れられます。
開口部を配置する際に注意すべきは道路を挟んだ反対側の建物からの視線です。
視線を意識せずに大きな開口を設けると常にカーテンを閉めた状態で暮らすことになるので、外部にルーバーを設置するなど、日光を通しつつ視線を通さない工夫が大事になります。
④メンテナンス性の低さを解消
隣家との間が狭く足場を配置できない場合は、「メンテナンスを行わない期間を長く取るよう設計」します。
具体的に、漏水の原因となる窓などの開口部は隣家側に作らず、道路側に作れば漏水リスクを減らすことができます。
さらに、壁面も耐用年数が長い素材・塗料を使用し、サイディングや防水シートも耐用年数が長いものを使用することで漏水のリスクを減らすことができます。
住宅は壁内に水が侵入することを最も嫌います。
長期間漏水を防ぐ対策を取ることで、メンテナンスしづらい環境を乗り切りましょう。
⑤収納の悩みを解消
土地や床面積が限られている狭小住宅では、「デッドスペースを見つけて収納として活用」することが大事です。
天井の上に広がる小屋裏、階段下のデッドスペースといった空間は収納によく利用されます。
地面からの湿気を受けるので使い方には注意が必要ですが、基礎の一部を収納として利用する方法もあります。
間取りや配置図を眺めて、収納として利用できそうなスペースを探してみましょう。
それでも収納が足りない場合は、トランクルームなど外部に荷物を預けるサービスを利用する方法もあります。
利用できるスペースやサービスは全て活用して、生活の利便性を上げましょう。

狭小住宅ならではのメリット

デメリットやその対策について確認しましたが、実は狭小住宅にはメリットもあります。
狭小住宅ならではの利点も確認してみましょう。
人気のエリアで土地を購入できる
都市部では土地価格が高騰しており十分な土地を購入するのは困難ですが、「土地面積を少なくすることで希望するエリアで土地を取得できる」可能性があります。
希望する学区や会社からの距離など様々な理由で土地探しのエリアが決まっている場合、購入する土地面積を減らすことは土地にかかる費用を抑える有効な手段といえるでしょう。
税金・維持費を抑えられる
住宅は購入してからも税金や維持費を支払う必要があります。
税金の中で固定資産税や都市計画税は土地の時価を元に算出するため、「所有する土地面積を小さくすることで支払う税金を抑える」ことができます。
家の規模や庭の面積を小さくすることも、家の維持費を抑える効果があります。
家や庭が大きいほど手入れやメンテナンスに手間や時間がかかるからです。
まとめ│工夫次第で狭小住宅でも快適に暮らせる

希望するエリアや予算の関係で家の規模が小さくなる場合、間取りや収納など様々な場面で制限が生じます。
一方で、制限と捉えず工夫で解決することに楽しみを見出だせれば狭小住宅であることはデメリットになりません。
大きな住宅を購入する場合に比べて維持費も抑えられるため、レジャーや趣味にお金を回すこともできます。
工夫を凝らして狭小住宅で快適に暮らしてみましょう。
ネクストハウスでは、自宅にいながらプロに相談できる「おうちでオンライン相談」を実施しています。
狭小住宅を検討中で疑問が浮かんだときは、お気軽にご相談ください。
家づくりのこと何でもご相談可能!「おうちでオンライン相談」実施