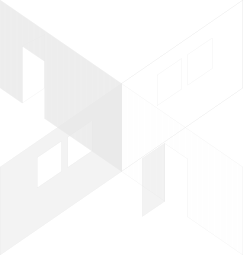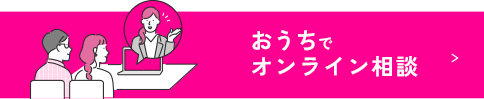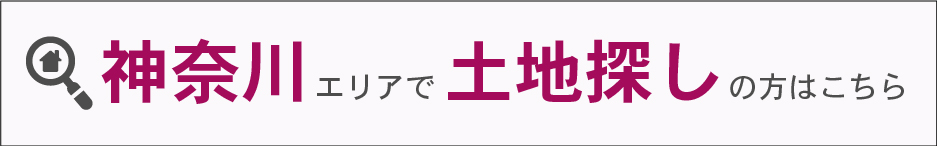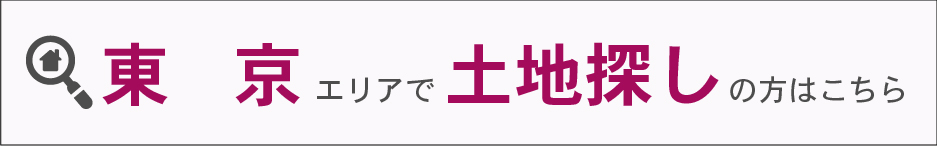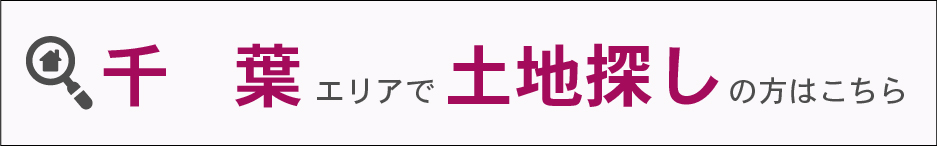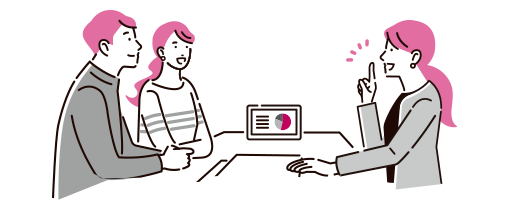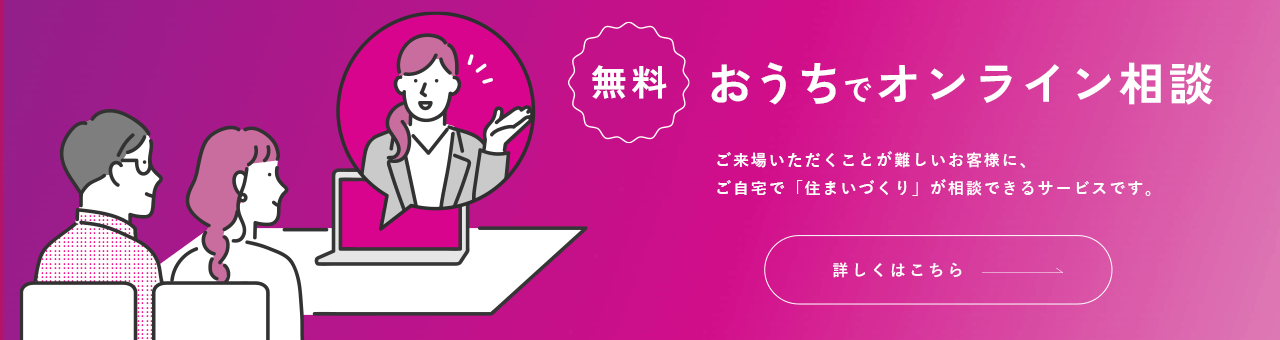目次
大型の家具が転倒してしまうのを防ぐツールとして「突っ張り棒」が人気です。しかし「突っ張り棒は意味が無い」という声もあり、実際の所どうなのか気になっている方は多いのではないでしょうか?そこで本記事では、突っ張り棒の役割や地震に強い家の間取りについて詳しくご紹介していきます。
コラムのポイント
・突っ張り棒は本当に意味が無い?役割やメリットを把握!
・地震に強い間取りのポイントを確認できます

突っ張り棒の役割・メリット

ここではまず、突っ張り棒の基本的な役割やメリットについてご紹介します。
地震対策としてホームセンター等で見かけることも多いですが、どんな役割があるのか整理しておきましょう。
地震対策になる
突っ張り棒とは、家具の安定性を確保するために使用されるアイテムのことを指します。
地震対策において重要で、ホームセンター等で手軽に購入できることから人気です。
突っ張り棒を設置することで構造を補強し、耐震性を向上するのに役立ちます。
地震が発生すると振動や揺れにさらされますが、突っ張り棒があることで、横方向の力に対する抵抗力を高められます。
具体的には、タンスやクローゼット、本棚といった大型で重量のある家具に設置されることが多いです。
家具の種類を選ばず設置できる
本来であれば、天井との隙間が無いピッタリの寸法の家具を配置するのが理想的です。
しかし気に入った家具や予算に見合った家具は、必ずしもピッタリの寸法ではない場合が多いです。
そのような場合には、突っ張り棒を使うことで耐震性を高められます。
突っ張り棒は、壁から天井までの空間に取り付けられるため、長さや高さを調整可能です。
これにより様々な高さや間隔に対応でき、異なる種類やサイズの家具に対して柔軟に設置できるのがメリットです。
突っ張り棒は意味が無い?デメリットや注意点

天井補強の必要がある
突っ張り棒は、天井面と家具面の間に負荷を掛けることで安定性を確保しています。
そのため、天井面にある程度の強度が求められる点には注意が必要です。
天井が十分に補強されていない場合には、突っ張り棒の設置が適していない可能性があります。
突っ張り棒を設置する前には、建物の構造をしっかりと確認しておきましょう。
天井補強が必要な場合は追加の補強工事が必要となり、費用や手間が掛かります。
設置位置を守る必要がある
突っ張り棒を使用する際には、正確な位置に設置する必要があります。
天井と家具との間で負荷が掛かるため、適切でない位置に設置されると安定性が損なわれて効果が得られません。
また、一度突っ張り棒を特定の位置に設置すると、簡単には位置を変更できません。
家具の配置変更や新しい用途への利用によって設置位置を変える場合、再調整や新たな突っ張り棒の設置が必要になります。
さらに突っ張り棒の長さには限界があるので、設置したい場所の床と天井の距離によっては、適切な長さの突っ張り棒が無い場合もあります。
突っ張り棒を使用する際には、正確な設置位置を守って慎重に調整するようにしましょう。
他アイテムとの併用がおすすめ
重い家具や大きな棚類を補強する場合、突っ張り棒だけでは不十分なことがあります。
そのため他の補強アイテムや家具の安定化手段を併用することで、より堅牢な構造を構築できます。
また突っ張り棒は一時的な使用には適していますが、長期間の使用には制限があります。
他の補強アイテムや構造的な変更を組み合わせることで、安定性を維持しつつ長期間の使用が可能になります。
デザイン性が低い
一般的な突っ張り棒は、機能性を重視した単純なデザインが多いです。
金属やプラスチックなどのシンプルな素材で作られ、無機質な色合いになっています。
そのため、室内のデザインやスタイルに対してあまり調和しないのがデメリットです。
これにより室内の他の家具やデザイン要素との調和が難しくなり、統一感が損なわれる可能性があります。
突っ張り棒をおしゃれに見せるには、木目調でナチュラルなタイプやシンプルな白の目立たないタイプを選ぶのがおすすめです。
場合によってはカーテンで隠す等、なるべく見せないようにする工夫をしましょう。

地震に強い間取りとは|計画ポイントやコツ

地震対策として突っ張り棒は有効ですが、なるべく間取りの段階から耐震性を意識しておくのがおすすめです。
ここでは、地震に強い間取りの特徴についてご紹介します。
正方形の間取りにする
正方形の間取りは、安定した対称性を持っているのが特徴です。
均等な配置により不均等な応力がかからないため、耐震性が向上します。
四隅が同じように配置されているため、比較的均等に耐震補強を行うことができます。
このような配置は、地震に対する強度を向上させる助けになります。
また正方形の間取りは室内の使い勝手が良く、家具や設備の配置がしやすいのも特徴です。
という利点があります。
地震時の安全性だけでなく、日常の快適な生活にも貢献します。
平屋は倒壊リスクが少ない

平屋は、地震に強い建物として人気が集まっています。
上の階を持たないため、構造的に重心が低くなるのが特徴です。
これにより地震の揺れに対する安定性を向上させ、建物が倒れにくくなります。
ただし平屋であっても、地域や建物の構造、素材などが安全性に影響を与えるため、地震対策には慎重な計画と専門家の助言が必要です。
建築基準や地域の耐震基準を遵守し、地元の建築業者や構造のプロに相談しましょう。
壁量を確保する
壁量とは、壁全体に対する耐力壁や構造耐力のことを指します。
壁量がしっかりと確保されていることで、地震時に発生する水平な力に対して抵抗し、建物の安定性を向上させる役割があります。
壁量を確保することで、適切な位置に耐力壁を設置しやすくなります。
最近では大きな窓を大胆に配置する間取りも人気ですが、耐震性の面からはあまりおすすめできません。
窓ガラスは構造的に脆弱になりがちなので、適切な分量に収める必要があるのです。
壁量の確保は、柔軟性と剛性のバランスを考慮する要素でもあります。
十分な壁量を持つことで建物の剛性や柔軟性が確保され、地震時の変形や揺れに対応できるようになります。
軽量な屋根材を使う

軽量な屋根材を使用することで、地震時に建物全体の重量が軽減されます。
地震においては建物の重量が大きいほど揺れに対する応答が強くなるので、軽量な屋根材を使うことで地震への影響を軽減できます。
具体的には、瓦屋根よりも金属の屋根材の方が軽くなります。
軽量な屋根は、建物全体の柔軟性を増加させます。
地震時に柔軟であることは、建物が揺れに対して柔軟に変形し、剛性の強い部分での集中的な応力を軽減します。
造作収納にする
造作収納とは、壁面に組み込む形で設置される家具のことを指します。
従来の住宅では大きなタンスやドレッサーといった家具を配置するのが一般的でしたが、最近では造作収納を設計段階で組み込むケースが増えています。
こうすることで家具の倒壊がそもそも起こらず、耐震性が上がります。
造作収納は、デザインと機能を調和させられるのもメリットです。
収納が壁に組み込まれているため、すっきりとした見た目にまとまります。
まとめ
本記事では「突っ張り棒は意味が無い?」というよくある疑問について掘り下げてご紹介しました。突っ張り棒は地震対策として有効ですが、本来であれば造作収納といった間取りで工夫するのがおすすめです。本記事でご紹介したポイントを参考に、住まいの地震対策を進めてみてはいかがでしょうか?
ネクストハウスでは実際のLDKを見学できるモデルハウスを東京・神奈川に複数ご用意しています。
お気軽にお越しください!

自宅にいながらプロに相談できる「おうちでオンライン相談」も実施しています。
豊富な経験からアドバイスできるので、ぜひお気軽にご相談くださいね。
家づくりのこと何でもご相談可能!「おうちでオンライン相談」実施