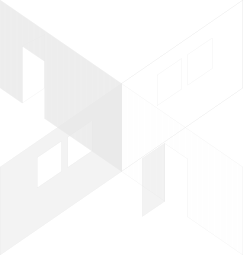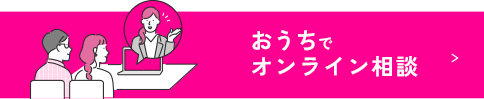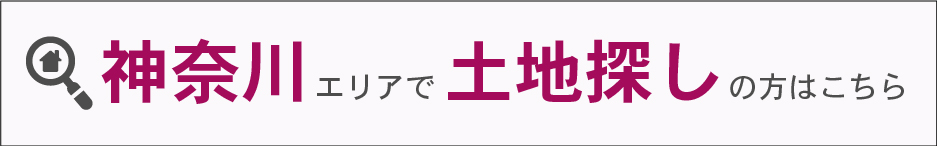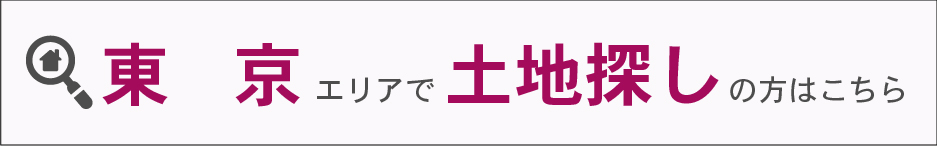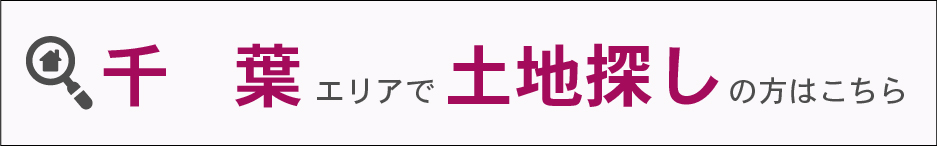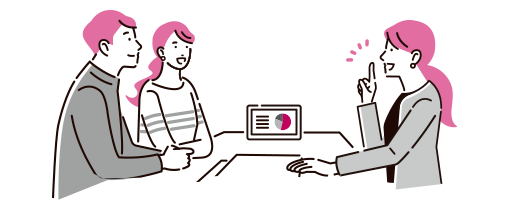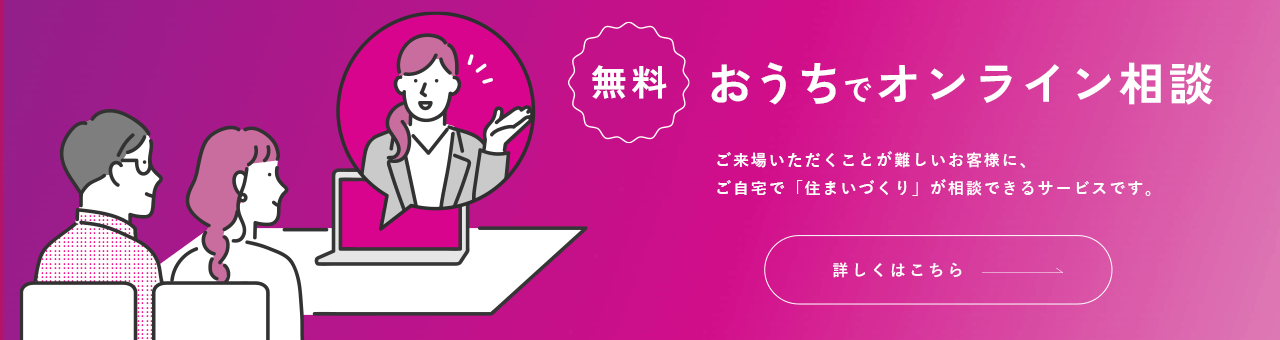「リビング学習」というキーワードが広く知られてから、キッチンから見える範囲で宿題や勉強を頑張る小学生が増えています。
そしてリビング学習が浸透すると同時に、「リビングが片付かない」ことに対するストレスも増加しているように思われます。
目の届く範囲で学習すると、子供がどんな勉強を行っているのかを知ることができます。
また、分からないことを父親、母親に質問することで親子のコミュニケーションが促進されることもメリットです。
リビングで学習すること、リビングを綺麗に保つこと、この2つを両立させるためにはどうすればよいのか本記事では解説します。
また、学習に加えてリビングに散らかってしまう「おもちゃ」の片付け方も一緒に紹介します。
片付いた綺麗なリビングを目指して、最後まで読んでみてくださいね。
・リビング学習用品を片付けるコツがわかる
・リビングまわりのおもちゃを片付けるコツがわかる
・リビングまわりの収納のコツがわかる
目次
■「リビング学習用品」を片付けるコツ
■「リビングまわりのおもちゃ」を片付けるコツ
■ リビングまわりの収納計画
■ まとめ│リビングの整理は「仕組みづくり」が大事。設計段階で計画しよう!
建築実例

「リビング学習用品」を片付けるコツ

最初にリビング学習用品の整理について解説します。
どうしてリビングが散らかってしまうのか原因を考えつつ、学校で使う道具を片付ける方法を紹介します。
「リビング学習用品」が散らかる理由
リビング学習用品が散らかるのは「常に新しいものが入ってくること」が原因です。
片付けは、元々置いてあった場所に出したものを戻すことが基本です。
一方で学校では毎日新しいプリントが配られ、学期が変われば新しい教科書を購入し、鍵盤ハーモニカなどの大物を持ち帰ることもあります。
このため、使ったものを戻すことに加えて、次々に入る新しいものを処理することが重要になります。
コツ① 学習用品の帰る場所を作る
新しい物を収納に上手く溶け込ませることも大事ですが、「学習用品の帰る場所を作る」ことが片付けの基本的なコツです。
ランドセルや筆記用具など、毎日使い、毎日持ち帰るものには必ず「帰る場所」を作り、他の場所に置かないことを徹底しましょう。
設計段階で子供の人数分の用品置き場を作り、帰る場所をしっかり準備しておくことも必要です。
コツ② スペースに余裕をもたせる
次に「スペースに余裕をもたせる」ことを考えましょう。
先述したとおり学用品は増え続けるので、十分な量の収納を確保することが望ましいです。
想定よりも少し多いくらいの場所を確保しておくことで、新しいものが配布されてもリビングに飛び出さず、備え付けの収納の中に収めることができます。
コツ③ 収納スペースは増やさない
カラーボックスの新規購入など「新たな収納スペースを増やさない」工夫も大事です。
学用品が増えて収納が不足すると、つい新しい収納を購入してしまいがちです。
小学校卒業まで物は増え続けるので、新しい収納を買い続けるいたちごっこになりかねません。
最初に想定した収納を超える量の物は廃棄を検討するか、または頻繁に使わないものは子供部屋に置くようにして、リビングのまわりは収納を増やさないようにしましょう。
コツ④ ざっと入れる大きなバスケットがあると便利
最後に、リコーダーや工作など「不定形のものを入れるバスケットを置く場所」を作っておくと便利です。
学校から配布される物は大きさが不揃いなことがあり、一品ごとに綺麗に収納しようとするとスペースを取られてしまいます。
大雑把に物を入れられるバスケットがひとつあれば、不揃いなものや細々としたものを一括して入れられるのでスッキリ片付けられます。
「リビングまわりのおもちゃ」を片付けるコツ

次に、リビングまわりが散らかる原因となる「おもちゃ」を片付けるコツを解説します。
特に子供が小さいとおもちゃが散乱しやすく、片付けた端から散らかるのでストレスを抱えている人もいるのではないでしょうか。
「リビングまわりのおもちゃ」が散らかる理由
おもちゃも上手に片付けるために、散らかってしまう原因を知る必要があります。
主な原因は「帰る場所が決められてないこと」と「片付けることを負担に感じてしまうこと」の2つです。
コツ① おもちゃの帰る場所を作る
勉強道具と同じで、おもちゃには「帰る場所」を作りましょう。
帰る場所=定位置を決めれば、どこにおもちゃを片付ければよいのかが明確になり、適当に片付けておもちゃの山が完成することを防げます。
リビング、ダイニング、和室、いずれかに必ずおもちゃを収納できるスペースを確保して、帰る場所を設定してあげましょう。
コツ② 完全な整理整頓を続けるのは無理と心得る
次に、おもちゃを「完全に整理整頓するのは不可能」と心得て、大まかに片付けられればよいと思いましょう。
おもちゃを分類して綺麗に片付けるのが理想ですが、毎回分類して整理すると子供は片付けを負担に感じてしまい、苦手意識を持ってしまいます。
ざっと片付けると発生する雑多な感が苦手な人は、おもちゃの定位置の前に引き戸やロールスクリーンなど、片付け後に視覚的に隠す工夫を考えましょう。
コツ③ リビングに持ってくるおもちゃは厳選する
おもちゃも学用品と同様に増え続けるものなので「リビングに置いておく物は厳選」して、収納に入りきらないものは子供部屋での保管、または廃棄や譲渡を検討しましょう。
入り切らないからと別途収納を購入すると、際限なくおもちゃが増えてしまうので注意です。
コツ④ 必ず毎日片付ける
最後のコツは「必ず毎日片付ける」ことです。
おもちゃの帰る場所を準備して、さらに大まかな片付けを許容すれば、片付けにかかる労力や時間は少なくなります。
必ず毎日定位置に片付けることを義務化して、毎日片付けることを徹底し習慣化すれば綺麗なリビングの実現に一歩近づきます。
床に物がなければ掃除機をかけるときの労力も節約できるので、抱えるストレスも少なくなるでしょう。
リビングまわりの収納計画

リビング学習用品やおもちゃを片付けるためのコツを解説しました。
最後に、片付いたリビングを実現するために設計段階で考えるべきことを紹介します。
デッドスペースを有効活用する
学用品やおもちゃを片付けるためには一定度の収納が不可欠です。
「デッドスペースを活用すること」で収納量のアップを図りましょう。
具体的には階段下のスペースの利用、キッチン背面への収納確保、小上がり和室の下部を収納にするなどです。
重要なことは、学習や遊ぶ場所の近くに確保して、使い勝手のよい収納にすることです。
頻繁に使用することが想定されるので、出し入れのたびに家具を動かすようでは使わない収納になってしまう恐れがあります。
ライフステージの変化に対応できるようにする
次に考えることは「ライフステージの変化に対応できるようにする」ことです。
学用品やおもちゃの収納に適した大きさの収納を作りますが、子供が成長して独り立ちしてからは趣味の品や生活用品を収納するようになるでしょう。
部分的に可動棚を採用して、収納するものの高さ・大きさが変化しても使える収納にしておくと、長く使える収納になるでしょう。
隠し方を考えておく
3つめは「隠し方を考えておく」ことです。
今回紹介した方法は大まかな片付け方を許容するもので、雑多な雰囲気が出てしまうことがあります。
急な来客時に片付けたものが見えることに抵抗を感じる人は、開き戸やロールスクリーンなど、隠す方法を考えておくとよいでしょう。
まとめ│リビングの整理は「仕組みづくり」が大事。設計段階で計画しよう!

学用品やおもちゃでリビングが散らかることを防ぐ対策、さらに対策を取るために必要な収納計画について解説しました。
リビングを継続して綺麗に保つためには「仕組みづくり」が大切です。
物に帰る場所を作り、サッと片付ける仕組みを作っておけば、毎日の片付けの手間が少なくなり日々の片付けの労力を低減でき、綺麗な状態を保つことができます。
設計段階で片付けの仕組みを検討して、綺麗なリビングを実現しましょう!
ネクストハウスでは、自宅にいながらプロに相談できる「おうちでオンライン相談」を実施しています。
リビングまわりの片付け方や収納方法で悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。