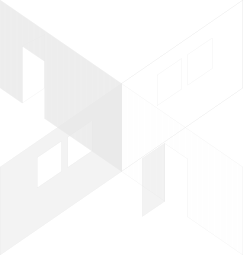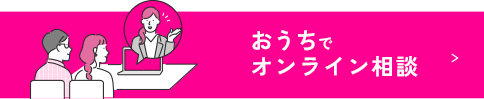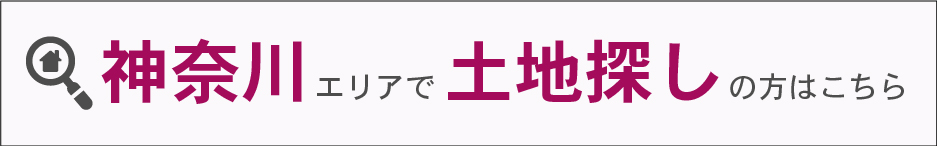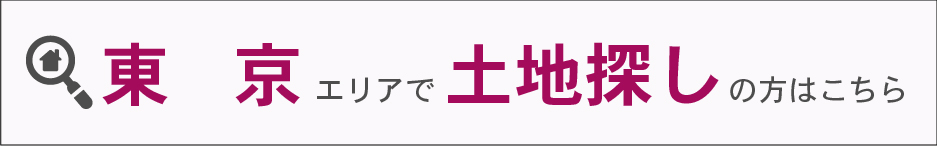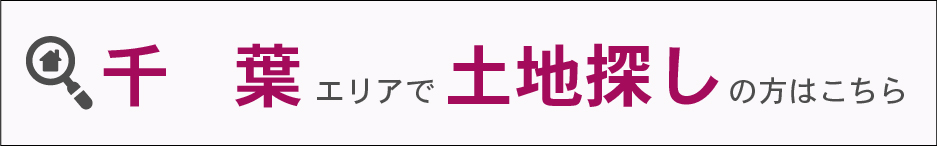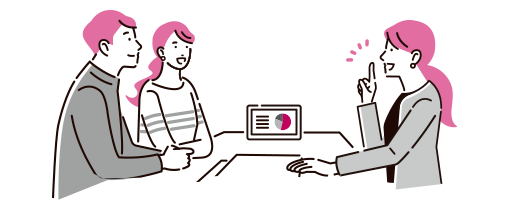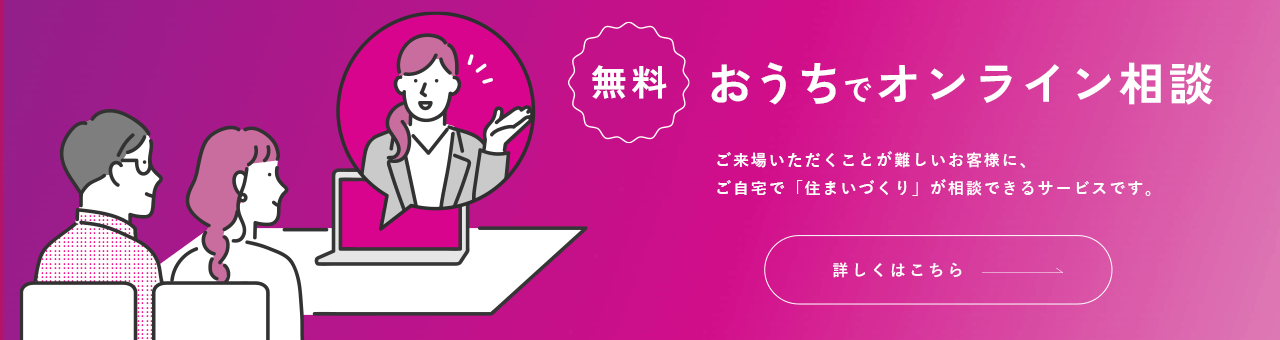目次
太陽光発電や省エネとあわせて「省エネルギー住宅」という言葉を聞いたことはありますか?
SDGsや環境問題が深刻化するなかで、住宅も省エネルギーであることが義務化されました。
本記事では、新築で家を建てる際に意識するべき省エネルギー住宅を作るポイントを紹介します。
さらに省エネルギー住宅に利用できる補助金についても解説していくので、ぜひ参考にしてください。
・省エネ住宅の「義務化」についてわかる
・省エネ住宅の「ポイント」がわかる
・省エネ住宅の「補助金」がわかる
目次
■2025年までに省エネ住宅が義務化
■省エネルギー住宅の基準とは
■省エネ住宅を作るポイント
■省エネ住宅で受けられる補助金
■まとめ│省エネ住宅に対応して未来につながる家に住もう
建築実例

2025年までに省エネ住宅が義務化

脱炭素社会の実現に向けて、2025年から新築住宅の省エネが義務化されることをご存じですか?
2020年以降のすべての新築住宅において、国が新たに定めた住宅省エネルギー基準をクリアしなければならなくなりました。
2025年までには新築住宅を建てる際に、建物の断熱性を高めて消費エネルギーを削減するなど、省エネ対策の強化が求められます。
さらに2030年には省エネ基準を「ZEHレベル」に引き上げ、新築住宅のすべてをゼロエネルギー住宅とすることを打ち出しています。
ZEHとは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略です。
住宅の断熱性・省エネ性能に加え、太陽光発電などによって創り出すエネルギーを組み合わせ、住宅の一次エネルギーの消費量を正味で、おおむねゼロ以下にする住まいを指します。
新築で住宅を建てたいと考えている方は、省エネ対策は必須の対応となることを覚えておきましょう。
省エネルギー住宅の基準とは

国は、省エネルギー住宅のベースとなる基準として「省エネルギー基準」を設けています。
これを上回る基準として「低炭素建築物の認定基準」と「住宅トップランナー基準」が設定されています。
住宅の省エネルギー基準
「住宅の省エネルギー基準」は、省エネルギー住宅の目安として1980年に省エネ法にて制定されました。
省エネルギーの性能の「外皮性能」は、住宅の窓や外壁の断熱性能により室内の温度を一定に保つことで評価されます。
また冷暖房や家電など、住宅全体で使用する「一次エネルギーの消費量」の二面から評価されます。
低炭素建築物の認定基準
「低炭素建築物」とは、建物内での生活や活動によって発生する二酸化炭素を抑制するために、低炭素化の措置が講じられている建築物のことです。
低炭素建築物の認定を受けるには、低炭素化に資する措置を2項目以上講じるか、標準的な住宅よりも一定以上削減されていると認められていなければいけません。
加えて一次エネルギー消費量が、省エネルギー基準に対して一定比率以上の削減がされている必要もあります。
住宅トップランナー基準
「住宅トップランナー基準」とは建売事業者や建設工事業者を対象にした基準で、分譲戸建住宅・注文戸建住宅・賃貸アパートについて、目指すべき省エネルギー性能を定めたものです。
住宅の省エネルギー基準と同様に、住宅の断熱性能の確保による外皮性能と、一次エネルギー消費量の削減を目的にしています。
分譲戸建住宅は2020年度まで、注文戸建住宅・賃貸アパートについては2024年度までに基準をクリアすることが求められています。

省エネ住宅を作るポイント

省エネルギーの住宅とは、どのような点を意識して作ればよいのでしょうか。
省エネ住宅を作るためのポイントについて解説していきます。
断熱性を高める
住宅内の温度が、夏や冬の外気に影響されないためには断熱性が重要です。
断熱の性能が低いと、冷暖房の効きが悪くなるため無駄なエネルギーを消費してしまいます。
住宅の断熱性を高めるためには、外気に接している外壁・床・屋根に断熱性の高い素材を使うか、断熱材で包み込むことが効果的です。
隙間が出来てしまうと、室内の熱が外に逃げたり、外の熱が室内にはいったりすることになり、室内の温度を一定に保てなくなります。
特に窓からは熱の出入りが大きいため、断熱の対応をする上で重要なポイントとなります。
遮熱対策をする
断熱性を高めると、室内に取り入れた熱を排出しづらくなってしまうため、夏場は遮熱対策が必要です。
特に窓の遮熱対策をすると、直射日光による熱を室内に取り入れることを防ぐことができ、冷房機器の効果を高められます。
窓の外側の対策では植物を植え、内側の対策としてはブラインドや遮熱複層ガラスの設置等により、太陽熱の遮断が可能です。
換気をする
断熱性や気密性を高めた住宅は、常に換気を行うことが重要です。
換気をすることで、住宅内に絶えず空気の流れを作ると、室内の温度が均一化されます。
快適な温度が保たれるだけでなく、シックハウスや結露を防ぎ、家を維持する観点でもメリットとなります。
省エネ住宅で受けられる補助金

省エネ住宅に対応する際には、国からの補助金が交付される場合があります。
新築のみでなく、リフォームの場合でも活用できる補助金もあるので、それぞれ紹介していきます。
こどもみらい住宅支援事業
「こどもみらい住宅支援事業」は、子育て世帯・若者夫婦が省エネ住宅を新築・購入する際に国の補助金が交付される制度です。
新築の場合は子育て世帯・若者夫婦の世帯を対象として最大100万円、リフォームの場合は全ての世帯を対象として最大30万円の補助金が交付されます。
対象となる子育て世代とは18歳未満の子どもがいる世帯、若者夫婦世帯は夫婦のいずれかが39歳以下の世帯のことを指します。
令和4年10月31日までに契約の締結を行い、住宅を整備・分譲する事業者による手続・登録を受け、着工したものが対象となります。
ZEH支援事業
「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業」は、断熱性を高めた省エネの実現と、太陽光発電設備などを取り入れた年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅に対して補助金が交付されます。
個人が対象となる戸建て住宅は、性能の違いに応じてZEH支援事業、ZEH+実証事業、ZEH+R強化事業で、それぞれ一戸当たり55~100万円の補助金が受けられます。
補助対象となるには、工事着手前に申請し審査を受ける必要があるので注意しましょう。
地域型住宅グリーン化事業
「地域型住宅グリーン化事業」は、長期優良住宅やゼロ・エネルギー住宅、低炭素住宅といった省エネルギー性能等に優れた木造住宅を新築する場合に交付される補助金です。
補助制度を受けるには、採択グループに属した地元の中小工務店で施工する必要があるため、補助金を検討している方は工務店選びから注意しましょう。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、今ある住宅を耐久性・耐震性・省エネ化して長く大切に住むために長期優良住宅化リフォームをする場合、工事費の一部に対して交付される補助金です。
補助金はリフォームを行う補助事業タイプによって、一戸当たり100~250万円の補助金が受けられます。
また、三世代同居対応改修工事を行う場合には、一戸につき50万円を上限に加算されます。
まとめ|省エネ住宅に対応して未来につながる家に住もう
省エネ住宅の義務化によって、新築住宅を検討している方にとって対応は必須となってきます。
しかし省エネ住宅にすることで多くのメリットもあります。
エネルギーの消費が少なくなれば、長期的にみて光熱費などの費用が大幅に抑えられることになります。
また大切に丁寧に暮らすことで、修繕や建て替えといった住宅にかける費用を抑えることにつながります。
省エネ住宅を建てることで受け取れる補助金なども活用して、大切に長く住める家づくりをしましょう。
ネクストハウスでは、自宅にいながらプロに相談できる「おうちでオンライン相談」を実施しています。
省エネ住宅はもちろん、長期で住める住宅づくりについて相談したいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
家づくりのこと何でもご相談可能!「おうちでオンライン相談」実施